
自然災害の備え|必需品リスト&防災を家族で習慣化するコツ
地震、台風、豪雨……。自然災害はいつ起こるか分からないからこそ、日頃からの対策が欠かせません。ここでは、自然災害に備えるための基礎知識や最低限揃えておきたい備蓄品リスト、ライフラインがストップした時に欠かせない電気・ガス・燃料対策、さらには「家族のルール」作りのポイントまで、具体的に紹介します。
自然災害への備えに必要な基礎知識

地震や津波など、自然災害には多くの種類があります。しかし、すべての災害に同じように備えることは現実的ではありません。まずは自分が住んでいる地域で発生確率が高く、被害が想定される災害に絞って対策することが重要です。ここでは、自然災害への備えを考えるうえで押さえておきたい基礎知識を解説します。
主な自然災害の種類一覧
ここでは代表的な自然災害の種類と、それぞれで想定される被害の一例を紹介します。
| 自然災害の種類 | 概要 | 被害の一例 |
| 地震 | 地殻の断層運動によって発生する揺れ | 建物の倒壊、津波の発生、インフラの寸断(例:2011年 東日本大震災) |
| 津波 | 海底地震や火山噴火などで発生する大規模な波 | 沿岸部の壊滅、人的・物的被害(例:2011年 東日本大震災による津波) |
| 台風 | 熱帯低気圧が発達した暴風雨 | 強風・豪雨による浸水、倒木、停電(例:2019年 台風19号) |
| 洪水 | 大雨や堤防決壊による河川の氾濫 | 家屋の水没、農作物の被害、交通網の寸断(例:2020年 九州豪雨) |
| 土砂災害(がけ崩れ・地すべり) | 豪雨や地震による斜面の崩壊 | 民家の埋没、人的被害(例:2021年 熱海土石流災害) |
| 火山噴火 | 火山活動によるマグマや火山灰の噴出 | 火砕流・降灰・避難被害(例:1991年 雲仙・普賢岳噴火) |
| 落雷 | 雷による電気的放電 | 山火事、感電事故、電子機器の故障 |
| 竜巻 | 上昇気流で渦巻状の風が発生する現象 | 建物の倒壊、送電線の破損、車両の転倒(例:2012年 茨城県竜巻被害) |
| 雪害(豪雪・雪崩) | 大雪や雪崩による災害 | 交通機関の麻痺、家屋の倒壊(例:1981年 新潟豪雪) |
備えるべきリスクの優先順位
すべての災害に同時に対策を行うことは現実的ではありません。そのため、まずは想定されるリスクを絞り込むことが重要です。特に優先すべきは、発生確率が高く、かつ被害が大きい災害への備えです。
自宅周辺のハザードマップや自治体のホームページなどで防災情報を確認すれば、どの災害が自分の地域でリスクが高いかを把握できます。優先順位を明確にすることで、備えがぶれることなく、日常生活に無理なく取り入れながら継続しやすくなるでしょう。
災害時に起こる生活の変化
電気・ガス・水道といったライフラインの停止は、生活に大きな影響を与えます。調理や照明、トイレの利用といった、当たり前に行っていることが一気に制限されます。そんな状況で在宅避難を選ぶ場合は、日常に近い生活をいかに維持するかがカギです。防災用品の活用や、水の使い方を工夫するなどして、生活の安全を確保することが重要です。
自然災害に備えたい基本のアイテム
災害時にまず必要なのは食料や水、衛生用品、照明などの生活必需品です。備蓄量は、大人1人あたり最低3日分、できれば1週間分の在宅避難が可能な量を目安にしてください。家族構成や年齢に応じて量や種類を調整しましょう。特に赤ちゃんや高齢者がいる家庭では、ミルクやおむつ、常備薬など、特有の必需品も忘れずに備えることが大切です。
最低限揃えたい備蓄品リスト

以下に、災害時に最低限揃えておきたい備蓄品をカテゴリ別にまとめました。家族構成や生活スタイルに合わせて必要なものを加え、備えを整えていきましょう。
| カテゴリ | 品目例 |
| 食料・水 | 飲料水(1人1日3L × 3日分)、レトルト食品、缶詰、乳児用ミルク、離乳食 |
| 衛生用品 | ウェットティッシュ、アルコール除菌シート、簡易トイレ、おむつ、生理用品 |
| 燃料・調理 | カセットコンロ + ガスボンベ(3日分目安で9〜12本)、固形燃料、キャンドル、着火用ライター、マッチ |
| 灯油(推奨) | 石油ストーブ + 灯油(1缶18L×1〜2缶)、灯油ポンプ、換気用グッズ |
| 電源・灯り | 懐中電灯、LEDランタン、モバイルバッテリー(満充電)、乾電池各種 |
| 情報・連絡 | 携帯ラジオ(手回し・乾電池)、家族の連絡先メモ、地域のハザードマップ |
| 救急・衛生 | 絆創膏、消毒液、常備薬、体温計、冷却ジェルシート、子ども用の風邪薬・解熱剤 |
| 防寒・寝具 | 毛布、アルミブランケット、カイロ(貼るタイプも)、着替え・下着 |
| 子育て用品 | おしりふき、ミルク、哺乳瓶、お気に入りのおもちゃや絵本 |
持ち出し袋と在宅避難に分けて準備する
災害時の備えは「避難所へ行く場合」と「自宅で避難生活を送る場合」の2通りに分けることが大切です。
持ち出し用の防災バッグには、命を守るものを中心に最小限のものを詰めましょう。水や非常食、救急用品、懐中電灯、貴重品などを、1人につき1袋を目安に準備すると安心です。一方で在宅避難用の備蓄は、数日間を自宅で生き延びるための備えです。ライフラインが止まった事態を想定して、食料や水、電池、燃料、衛生用品などを準備しましょう。
持ち出し袋と在宅備蓄では、目的・必要量・中身が異なるため、混同しないことが大切です。実際の避難行動を家族でシミュレーションして、分担や保管場所を見直すとより効果的な備えが可能です。
防災バッグに入れるグッズは、こちらを参考にしてください。
防災バッグの中身リスト|最低限必要なものや準備・管理のポイントを解説
100均やスーパーを活用して手軽に揃える
防災用品を揃える際には、100均やスーパーを活用するのがおすすめです。普段の買い物の延長で必要なものを手に入れられ、価格も比較的手ごろです。特に100均では小分けタイプや使い切りの製品が多く、防災バッグに入れる分を用意したり、家族構成に合わせて買い足したりするのに便利です。
▼こちらの記事もご参考ください。
100均防災グッズ完全リスト|日常の延長でできるカンタン備え術
自然災害への備えには電気や燃料対策も重要

自然災害が起きると、電気・ガス・水道といったライフラインが同時に止まる可能性が高まります。特に電気やガスは、暖房・調理・通信・照明など、暮らしを支える存在です。災害時に備えて、複数の代替手段やエネルギー源を確保しておくことが安心につながります。
電気が止まった時の備え
停電が起きると、照明や冷蔵庫、暖房など、日常生活の多くがストップしてしまいます。特にスマートフォンは安否確認や情報収集に欠かせないため、充電用のモバイルバッテリーを複数用意しておくと安心です。さらに手回しラジオやソーラー充電器、長期停電に備えた容量の大きなポータブル電源なども、いざという時に頼れる存在です。
また冷蔵庫が使えなくなることも考え、冷凍庫には保冷剤を常備しておきましょう。食品を一時的に冷やせるよう、クーラーボックスも準備しておくと便利です。
▼こちらの記事もご参考に。
ガスが止まった時の備え
ガスが止まると、調理やお湯の用意ができなくなります。過去の災害では、お湯が作れず赤ちゃんのミルクを準備するのに苦労したという声もありました。カセットコンロと予備のガスボンベを備えておくと、簡単な調理や湯沸かしが可能です。ガスボンベは1日2本を目安に、最低3日分(6本)あると安心です。お風呂が使えない場合に備えて、ボディシートやドライシャンプー、防寒グッズも揃えておくと便利です。
灯油や燃料の備蓄も忘れずに
災害対策で見落としがちなのが、灯油など燃料の備蓄です。特に灯油ストーブは、停電時でも使用できる心強い暖房器具として注目されています。寒冷地では、命に関わるほどの冷え込みも想定されるため、灯油や燃料の確保は非常に重要です。
石油ストーブについて詳しく知りたい方は、こちらも参考にしてください。
石油ストーブのメリットとデメリットを解説。選び方や使用時の注意点も
自然災害が発生した際には、安全な場所に車を停めて車内で過ごす「車中泊避難」を選ぶ場合もあります。特に子どもやペットがいる家庭では避難所での生活が難しいことも多く、エアコンや車内の充電設備を活用できる点で安心です。そのため、日頃から車の燃料を満タンにしておく習慣を持つことが大切です。
こちらの記事では、車中泊避難について詳しく解説しています。
車中泊避難とは?災害時に安全に過ごすための備え・ポイント・注意点を解説
自然災害の備えに役立つ家族ルール

自然災害への備えでは、防災グッズの準備と同じくらい、災害発生時の行動を家族で共有しておくことも重要です。日常生活の中で無理なく実践できるルールや工夫を取り入れることで、家族全員が「自分ごと」として防災に取り組める体制を整えましょう。
平日昼間の災害を想定する
自然災害は、家族全員が一緒にいる時に起こるとは限りません。だからこそ平日昼間のように家族が別々に過ごしている時間帯を想定し、行動パターンを事前に整理しておくことが重要です。連絡手段や集合場所を具体的に決めておくことで、万が一の際にもスムーズに対応できます。さらに実際にシミュレーションを行うことで、問題点や改善点を事前に把握できるでしょう。
連絡手段と集合場所の確認
災害時は電話がつながりにくくなることがあります。そのためLINEや災害用伝言ダイヤル、自治体アプリなど、複数の連絡手段を用意しておくことが大切です。また家族全員が確認できる集合場所を決めておくことで、安否確認を迅速に行うことができます。さらに定期的に家族で情報を更新し、実際に実践可能な方法を共有しておくことも重要です。
食料品はローリングストック法で備蓄を回す
食料品の備蓄には、普段食べ慣れた食品を少し多めに買い置きして防災用として備える「ローリングストック」という方法がおすすめです。災害時でも普段に近い食事をとれることで、心の安心につながります。定期的に買い足すだけで備蓄を自然に継続でき、習慣化しやすい点もメリットです。消費期限を確認し、古いものから順に使うことで無駄を減らせます。さらに、パントリーなどで見やすく管理し、週単位で確認するとより効果的です。
自然災害への備えを家族の習慣に

自然災害への備えは、発生確率や被害の大きさを考慮し、優先順位をつけることが重要です。ライフライン停止に備えて、持ち出し袋と在宅避難用の備蓄を分け、それぞれの目的に応じて使い分けましょう。食料や水はローリングストック法で、消費しながら定期的に確認・買い足すことで備えを維持できます。100均やスーパーで手軽に揃えられるアイテムを活用するなど、日常生活に防災を組み込む工夫により、家族ぐるみで災害対策を習慣化しましょう。
#自然災害
#防災グッズ
合わせて読みたい
-

2025/12/18
灯油
灯油の臭いを消すには?車内やカーペットなど場所別の速攻対処法を紹介
#灯油 #防災備蓄
-
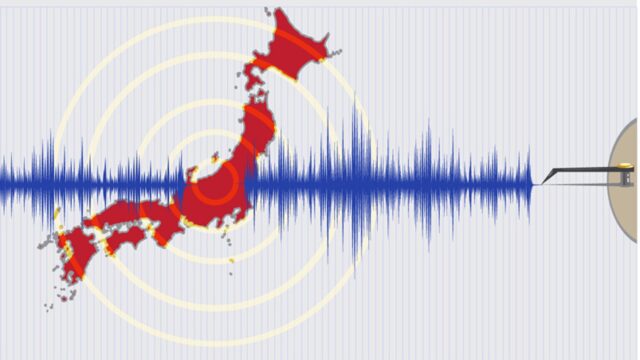
2025/12/16
南海トラフ
首都直下地震はいつでも起こりうる!発生確率や想定被害、今できる備...
#地震
-

2025/11/25
ライフスタイル
ポリ袋調理で災害時も温かい食卓を。備蓄食材を活用した非常食レシピ集
#日常生活 #防災
-

2025/10/30
フェーズフリー
防災視点で選ぶキャンプ用品│使い慣れたギアで災害時の安心を守ろう
#キャンプ #防災グッズ
-

2025/10/20
防災
非常用トイレの正しい使い方や準備のポイント|災害時に困らないため...
#防災グッズ #非常用トイレ
-

2025/10/13
ローリングストック
一人暮らしに必須の防災グッズ完全ガイド|必要なものリストや選び方...
#ローリングストック #防災グッズ #防災ポーチ


