
台風対策|窓ガラスを守る現実的な方法とおすすめの補強アイテムを紹介
毎年のように台風が日本列島を直撃し、住宅への被害が後を絶ちません。中でも窓ガラスの破損は、風雨や飛来物によって二次被害を引き起こすおそれがあります。この記事では、窓ガラスの応急処置から本格的な対策、さらに“その先”に必要な備えまで詳しく解説します。
台風で窓ガラスが割れる原因とは?

毎年のように発生する台風では、大きな被害のひとつとして「窓ガラスの破損」が挙げられます。その原因やメカニズムを知ることが、適切な備えをするための第一歩となります。
窓が割れる原因は「飛来物」と「風圧」
台風時の窓ガラス破損の多くは、強風で飛ばされた植木鉢や看板などの直撃によるものです。特にベランダや庭にある軽い物ほど、風で飛ばされやすくなります。
また、風圧だけで窓が内側から押し出されるように割れてしまうこともあります。築年数の古い住宅や一枚ガラスの窓は、破損リスクが高いため注意が必要です。
ガラスが割れるとどうなる?二次被害のリスク
割れたガラスの破片は鋭く、室内に飛び散ることでけがや失明のリスクがあります。窓から風雨が吹き込むことで、家具や床、電化製品に被害が及びます。
風の通り道ができると、屋根が浮き上がり、建物全体の構造にダメージを与えることも。 まずは「ガラスを割らせない」ことが、家族と家を守る台風対策の大切です。
「養生テープだけ」で本当に大丈夫?

SNSやニュースで見かける「窓に×印の養生テープ」は、一見対策をしたように感じられますが、あくまで“応急処置”にすぎません。その効果の限界を理解した上で、正しい備えを選びましょう。
テープや段ボール補強は“応急処置”でしかない
養生テープで窓に×印を貼る方法は、ガラスが割れた際の飛散をわずかに抑える程度の効果しかありません。ガラス自体の強度が上がるわけではなく、飛来物が直撃すれば普通に割れてしまいます。
段ボールを貼る方法も見られますが、防水性や耐風性には限界があります。“とりあえず”の対処ではなく、“備える”意識を持つことが重要です。
カーテン・新聞・突っ張り棒の実際の効果とは
厚手のカーテンを閉めておくことで、窓ガラスが割れた際のガラス片の飛散防止にはある程度効果があります。新聞紙を貼る方法も手軽ですが、水に弱く、強風には耐えられません。
突っ張り棒でカーテンを固定して強化するアイデアもありますが、窓そのものの強度には影響しません。これらの方法はいずれも“ないよりはマシ”程度の対策であり、過信は禁物です。
見落とされがちな「窓周辺の飛来物対策」
窓ガラスが割れる原因の多くは、「窓周辺から飛んできた物」であることを忘れがちです。ベランダの植木鉢や物干し竿、カバー類なども、強風によって飛来物になる可能性があります。
対策は「ガラスに貼る」だけでなく、「物を飛ばさないようにする」こととセットで考えましょう。台風が来る前に周囲を見直す習慣をつけておくことが、安全への第一歩です。
窓ガラスの台風対策にはどんな方法がある?

台風による窓ガラスの破損は、日常的な備えと対策によって大きく減らすことができます。手軽にできる応急処置から、専門的な施工を伴う本格的な対策まで、状況に応じて選ぶことが大切です。
ここでは、代表的な窓ガラス対策を3段階に分けて紹介します。
簡易・応急策(段ボール/新聞/カーテンなど)
手元にある物で対策したい場合は、段ボールや新聞紙を窓に貼る方法があります。厚手のカーテンを閉めておくことで、ガラスが割れた際の飛散防止にも多少の効果があります。
ただし、これらは強風や飛来物による破損を防ぐ力はほとんどなく、あくまで“応急処置”にすぎません。過信せず、台風前の一時的な対策として捉えておくことが大切です。
中期対策(飛散防止フィルム/プラダン)
飛散防止フィルムは、窓に貼ることでガラスが割れた際の破片飛散を防ぐのに効果的です。プラダン(プラスチック段ボール)を窓の内側に貼れば、緩衝材としての役割も果たします。
どちらもDIYで比較的安価に導入できるため、準備しやすい中期対策といえるでしょう。ただし、衝撃を完全に防ぐ物ではないため、飛来物への備えとしては不十分な場合もあります。
本格対策(雨戸/シャッター/合わせガラス)
最も信頼性が高いのは、雨戸やシャッター、防災合わせガラスといった本格的な対策です。雨戸やシャッターは飛来物の衝突を物理的に防ぎ、強風時の安全性を大きく高めてくれるのが特徴です。 合わせガラスは、特殊フィルムを挟んだ構造により、割れても破片が飛び散らず、外部からの侵入も防げます。初期費用はかかりますが、長期的に見れば「命と家を守る投資」としての価値は十分にあります。
台風直前・当日にやるべきことチェックリスト

台風が接近した際は、窓の補強だけでなく、家全体の安全確保が重要です。被害を最小限に抑えるためにも、すぐに実行できる行動を具体的に確認しておくことが大切です。
直前や当日に備えて、やるべきことをチェックリストで確認しておきましょう。
外にある“飛びやすい物”を屋内へ
ベランダの植木鉢や物干し竿、サンダル、ゴミ箱などは、すべて屋内へ避難させましょう。軽い物は強風で飛ばされ、窓ガラスに直撃する原因になります。
エアコンの室外機カバーや自転車のかごカバーも、事前に外しておくと安心です。周囲の住宅への被害を防ぐ意味でも、飛散物の撤去は最優先の対策です。
窓のロック・内側補強・カーテン閉め
窓のクレセント錠(鍵)はしっかりロックし、隙間風が入らないよう密閉しておきましょう。窓ガラスには内側からプラダンや飛散防止フィルムを貼って補強しておくと安心です。
また、厚手のカーテンやブラインドを閉めておくことで、ガラスが割れた際の飛散被害を軽減できます。小さな工夫の積み重ねが、大きな被害の防止につながります。
非常食を準備しておく
ライフラインが止まると、買い物に行けず冷蔵庫も使えなくなることを想定しておく必要があります。缶詰、レトルト食品、インスタント麺、栄養補助食品などは、最低でも3日分は備蓄しておきましょう。
加熱不要でそのまま食べられる物を多めに備えておくと、安心感が増します。カセットコンロやポータブルバーナーがあれば、温かい食事も確保できます。
停電・断水を見越した室内備えの準備も
懐中電灯やモバイルバッテリー、ラジオ、乾電池などは、すぐ使えるように準備しておきましょう。断水に備えて、飲料水やトイレ用の水、お風呂の残り湯の確保も忘れずに。
冷蔵庫の食材は停電前に早めに消費し、冷凍品はジップ袋にまとめて保冷剤代わりにすると便利です。エアコンが使えなくなることを想定し、暑さや寒さに対応できるよう、扇風機や灯油ストーブなども備えておくと安心です。
ガラス対策のその先”にある備えも忘れずに

窓ガラスの補強や飛来物対策は、台風対策の基本です。ですが、それだけでは守りきれない“その先にあるリスク”にも目を向けることが大切です。停電や断水、避難といったライフラインが絶たれる事態にも備えておきましょう。
台風前のガソリン満タンが避難・発電の命綱になる
台風前には、車のガソリンを満タンにしておくことは防災の基本。避難所への移動や、高齢者・子どもを乗せた緊急時の移動にも、燃料の確保は欠かせません。家庭用発電機を備えている場合も、ガソリンは停電時の重要な電力供給源です。
灯油を+1缶備えておけば、停電時の暖房・調理が可能に
秋冬の台風や寒冷地では、停電が寒さとの戦いにつながることもあります。灯油ストーブがあれば、電気が止まっても部屋を暖めることができ、明かりにもなります。
湯沸かしや簡単な調理ができるモデルなら、暖と食の両方をカバーできて安心です。普段から灯油を使っている家庭は、「+1缶」の備蓄を心がけておくと安心です。
防災意識が高い人ほど意識すべき「エネルギーの備蓄」
食料や水の備蓄と同じくらい大切なのが、「エネルギー」の備えです。停電が長引けば、照明や冷蔵庫、通信手段などがすべて使えなくなります。
モバイルバッテリー、発電機、灯油、ガスボンベなど、多様なエネルギー源を備えておくことが重要です。「電気が止まっても何が使えるか?」を家族で共有しておきましょう。
“備えは分散して重ねる”ことが安心につながる
「備えはひとつでは足りない」と考えることは、防災を考える上で欠かせません。発電機に加えてモバイルバッテリー、ガス、灯油などを組み合わせた分散型の備えが理想です。
使う人や場所、時間帯に応じて備えを重ねておくことで、さまざまな状況に柔軟に対応できます。“ひとつがダメでも他がある”という状態こそが、本当の安心につながります。
窓ガラスの対策+エネルギー備蓄で“命を守る防災”を

窓の補強だけで終わらないのが、これからの台風対策です。飛来物への備えに加え、ガソリンや灯油といった“エネルギーの備え”も、災害時の安心につながります。「少し多めに備える」ことを意識して、家族と暮らしを守るための防災を始めましょう。
#台風
#台風対策
#災害対策
#防災
合わせて読みたい
-

2026/01/22
停電対策
停電時に役立つ家庭用発電機とは?種類やメリット・デメリット、注意...
#灯油 #防災グッズ
-

2025/12/18
灯油
灯油の臭いを消すには?車内やカーペットなど場所別の速攻対処法を紹介
#灯油 #防災備蓄
-
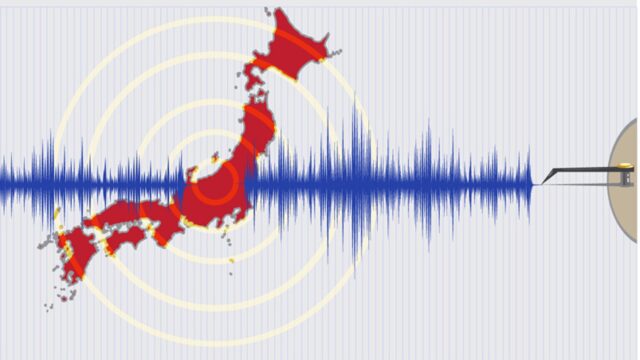
2025/12/16
南海トラフ
首都直下地震はいつでも起こりうる!発生確率や想定被害、今できる備...
#地震
-

2025/11/25
ライフスタイル
ポリ袋調理で災害時も温かい食卓を。備蓄食材を活用した非常食レシピ集
#日常生活 #防災
-

2025/10/30
フェーズフリー
防災視点で選ぶキャンプ用品│使い慣れたギアで災害時の安心を守ろう
#キャンプ #防災グッズ
-

2025/10/20
防災
非常用トイレの正しい使い方や準備のポイント|災害時に困らないため...
#防災グッズ #非常用トイレ


