
遊びが“備え”に変わるとき。アウトドアの達人に聞く“楽しく防災”の始め方
アウトドアは防災の訓練にもなる——そう語るのは、アウトドアライフアドバイザーの寒川一(さんがわ・はじめ)さん。
中学生の頃から趣味として楽しんできたアウトドアを、“遊び”にとどまらない“生きる力”として発信し続けています。
今回は自然の中で遊びながら、もしもに備える知恵と工夫を伺いました。
| アウトドアライフアドバイザー 寒川 一さん 自然災害が日常化する現代に向けて、“遊びながら備える”ライフスタイルを提案するアウトドアライフアドバイザー。北欧の自然享受文化に共感し、暮らしにアウトドアの知恵を取り入れる活動を続けている。東日本大震災や自身の避難経験をきっかけに、災害時に役立つキャンプ道具やスキルの活用法を伝える啓発にも力を注ぎ、アウトドアガイド、メーカーアドバイザー、テレビ・ラジオ・雑誌出演など、多方面で活躍中。 |
遊びながら“もしも”に備える、アウトドア防災という発想

「僕がアウトドアを防災の視点でとらえるようになったのは、2011年の東日本大震災がきっかけでした」と、寒川さん。
当時は神奈川県に住んでいて直接の被災はなかったものの、寒い体育館で毛布をかぶって過ごす人々の姿をニュースで見るたびに、胸が締めつけられたと言います。
「段ボールを敷いて寒さをしのぎ、プライバシーがまったくない避難生活。温かい食事にもありつけない状況を見て、『自分たちが普段遊びで使っている道具があれば、もっと快適に過ごせるのに』ともどかしく思っていました」
寒川さんは中学生の頃からアウトドアを楽しみ、数十年にわたりキャンプを続けてきました。テントや寝袋、マットといった道具は居住性が高く、快適に過ごせる性能を備えているものも多くあります。

「アウトドア用品は、非常時の安心につながる」。その思いを行動に移し、翌2012年から「アウトドアと防災」をテーマに寒川さんは活動をスタート。火の起こし方や非常時に役立つ道具の使い方を伝えるワークショップをはじめ、今も各地で伝え続けています。
「キャンプって、ライフラインのない場所で衣食住を自分で組み立てる遊びなんです。いわば “人間の暮らしの縮図”ですよね。だから、その経験はそのまま“生きる力”につながりますし、防災に役立ちます」
火・水・食を自分でまかなう力が、非常時にも役立つ

火を起こし、水を確保し、食事をつくる——。その一連の流れは、生きるための基本そのものです。
特に水は、命をつなぐうえで欠かせない要素。寒川さんは、水源がないキャンプ場でキャンプをすることもあり、水の確保の重要性を実感していることから、日常生活の中でも備えを意識していると言います。
「まずは浴槽に水をためておく習慣をつけること。僕自身はやかんやポットも常に水を満タンにして、毎日使いながら入れ替えるようにしています」
そして火は、食事をつくったり暖をとったり、身を守る灯りとしても必要なもの。キャンプでの火起こしは、非日常体験ができる“楽しさ”とともに、子どもたちの学びになるそうです。
「火はどこまでが安全で、どこからが危険なのか。急な天候の変化にどう対応し、コントロールできない自然の中で快適さをどう探すか。どれも体験しないと学べないことです」
アウトドア用品は“暮らしの防災ツール”になる

「キャンプではよく忘れ物をするんですけど(笑)、そのときに今あるものでどうカバーするかを考えるんです。木を組み合わせたり、道具を別の用途で使ったり。これって防災に直結する創意工夫の訓練なんですよね」
アウトドア用品の中でも、特に防災グッズとして優秀だという、ナイフとロープ。シンプルで原始的な道具には、ものを創造する奥深い使い方ができるそう。
「例えばナイフは、いわば“道具をつくれる道具”です。木を削ればお箸やペグ(杭)、さらに薄く削れば天然の着火剤がつくれます。ロープはたった1本でも、結び方や活用場所を変えることで、ものを吊るしたり固定したりと、暮らし自体を快適にできる力を秘めています」

道具の便利さだけに頼ると、それがないときに自分の生活が成り立たなくなることもあると、寒川さんは言います。一方で、現代の便利な道具は、原始的な道具にはない安心感をもたらしてくれます。
「例えばソーラーパネルやポータブル電源は、長期の避難生活で頼もしい存在です。車中泊のキャンプをするときは、走行中にポータブル電源を充電し、停車中はそれを使って、車のエンジンをつけずに電力をまかなうこともあります」
ものをつくり出せる古い道具と、便利な新しい道具を、うまく組み合わせること。これが、寒川さんが考えるこれからの防災スタイルです。
「どちらを取ってどちらを捨てるかではなく、いいところを全部取り入れる。選択肢を増やすことが大切ですね」

またアウトドアで使う食器や寝袋、石油ストーブは、普段の生活にも取り入れているという寒川さん。
「普段から使い慣れていると、キャンプ場や避難所でいざ使おうとしたときに抵抗がないんです。慣れ親しんでいるものを持っていくという感覚になれるので、子どもでも自然に使えて安心できます」
寒川さんのご自宅でも、暖を取るために冬場は石油ストーブを2台ほど使っているそうです。
「エアコンや電気ヒーターに比べて、石油ストーブは空間が温まるのが早いんですよ。停電しても使えるので、安心感があります」と話します。灯油も常に2〜3缶ほど備蓄し、なくなりかけたら早めに買い足すようにしているとか。
「日常生活や趣味のキャンプの一環で燃料を備えておけば、無理なく続けられる防災対策になります。いざというときに“特別な準備をしておく”という感覚ではなく、“いつもの延長”で備えられることが理想ですね」
ただし石油ストーブなどの暖房機器を使用する際には注意点もあります。
「液体燃料は、保管の仕方に特に注意が必要です。液体の怖さは、倒してしまったときにカバーのしようがないこと。だから、ストーブのタンクに入れっぱなしにしないようにしています」
さらに、寒川さんは換気の大切さも強調します。
「例えば車の中といった密閉性の高い場所で、燃料系のアイテムを使うことは非常に危険です。一酸化炭素中毒のリスクがあるので、必ず換気をしてください」
車中泊キャンプの実感から――満タン習慣を始めよう

定期的に車中泊キャンプをするという寒川さん。その経験から、車は単なる移動手段を超えた存在だと言います。
「もし家が倒壊したり、在宅が困難になったりした場合、生活の拠点になるのは車です。車は移動できるのがメリットと取られがちですが、実はシェルターとしての役割が大きいと思っています。例えば上から雹が降ってきたり、石や瓦が落ちてきたりしても、車の中にいれば安全ですよね」
寒川さんは3日ほど寝泊まりできるように、非常用品やアウトドア用品を車載しているそう。さらには、ガソリンを満タンにしておくことも忘れません。「車のガソリンはなるべく忘れないよう、半分くらいの残量になったら入れるように心がけています」

「私は防災を日常化していくことをテーマにしています。災害が起きてからのアクションでは遅いんです。だからこそ、日頃の習慣が重要だと思っています」
寒川さんがガソリンスタンドでパニックバイを起こしているのを見たのも、東日本大震災のときでした。いつ給油できるかわからないほど長蛇の列になっていたそうですが、幸い、寒川さんたちはガソリンがあったので列に並ぶ必要はなかったそうです。
「みんなが普段からガソリンを満タンにしておく習慣がついていたなら、あのとき大行列にはならなかったかもしれません。普段の意識でいざというときのアクションは変わってくるので、必要なものは平時から備えておくことで、災害時は冷静に動く、これが大切だと思います」
「遊びの延長に、備えがある」寒川さんから読者へのメッセージ

「防災を日常と切り分けて考えるのではなく、日常の中に防災を溶け込ませていくという感覚を持ってほしいです。ただ、防災という言葉の持つネガティブさもよくわかるので、アウトドアという遊びのチャンネルで経験しておけば、何か起きたときに役立つと思っています」
あくまでも遊びの延長でいい、寒川さんは力強い言葉で背中を押してくれました。
#アウトドア
#インタビュー
#有識者
合わせて読みたい
-

2025/12/01
有識者インタビュー
「また同じことが起きても、備えがあれば変わる」──能登の経験から伝...
#インタビュー #地震 #能登半島地震
-
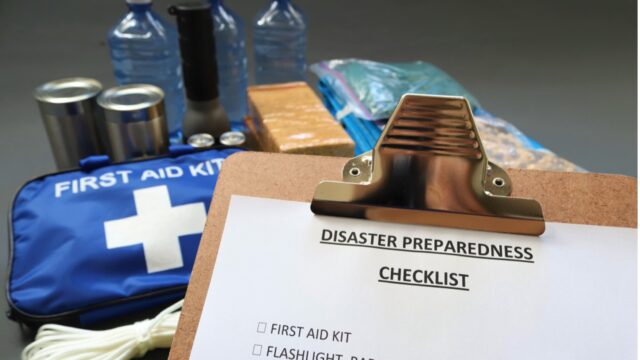
2025/11/27
ライフスタイル
防災備蓄品リスト完全ガイド|家庭と企業で備える必需品と管理のコツ
#日常生活 #防災グッズ #防災備蓄
-

2025/11/25
ライフスタイル
ポリ袋調理で災害時も温かい食卓を。備蓄食材を活用した非常食レシピ集
#日常生活 #防災
-

2025/11/13
ライフスタイル
ローリングストックで備える非常食|適した食品や実践のポイントを解説
#ライフスタイル #ローリングストック
-

2025/10/16
ライフスタイル
防災グッズでいらなかったものとは?本当に必要なもの7選も紹介
#ライフスタイル #防災グッズ
-

2025/10/01
有識者インタビュー
防災活動に取り組む現役消防士に聞く“いのちの守り方”
#インタビュー #防災 #防災意識



