
防災グッズでいらなかったものとは?本当に必要なもの7選も紹介
防災グッズを準備しても、実際に被災してみると「これはいらなかった」と気づくことがあります。ここでは被災者の声をもとに「いらなかった防災グッズ」と「本当に必要な防災グッズ」のリスト、さらに自分に合った備えをするポイントを紹介します。家族構成や住んでいる地域、生活スタイルに合わせて効率良く防災グッズを準備しましょう。
防災グッズでいらなかったもの5選

被災した人の感想を聞くと、実際には使わなかった防災グッズもいくつかあるようです。一般的な市販の防災セットに入っているけれど意外と使う場面が少なかったり、防災用に準備したものの実際には使いづらかったりするグッズを「いらなかったもの」として紹介します。
コンパス
北の方角を示すコンパスが、実際の避難行動で役立つ場面は少ないといえます。自宅周辺で被災した場合、周囲の道路や地理状況を把握していることがほとんどなので、必ずしも必要ではありません。コンパスの代わりにハザードマップの確認、オフライン環境でも使えるスマートフォン用の地図アプリをインストールしておくなどの準備をしておくことが大切です。
ロープ
災害時に人命救助やがれきの撤去、高所からの避難などにロープが使われる場面があります。しかし、扱いに慣れていないと実際に使いこなすのは難しく、出番がなかったという声も聞かれます。結び方に不慣れだと、かえって危険になることがあります。
ヘルメット
ヘルメットは命を守る重要な防災用品ですが、大きくかさばるのが難点です。家族全員分を揃えると、置き場所に困ることもあるでしょう。折りたたみ式など収納しやすいタイプを検討するのがおすすめです。
カップ麺
非常食として常備している人も多いカップ麺ですが、「停電でお湯が沸かせず、結局食べられなかった」という被災者の声も。調理に水が必要で、さらにお湯を沸かす手間がかかるのがネックです。その点、温めるだけで食べられるレトルト食品や缶詰のほうが、実際には活躍する場面が多いといえるでしょう。
ろうそく
停電時の明かりとして使えるろうそくですが、火がむき出しで倒れやすく、目を離した時に周囲に燃え移るリスクがあります。安全に明かりを確保するなら、ランタンやライトの準備がおすすめです。
本当に必要な防災グッズ7選

次に、災害時に最低限揃えておきたい防災グッズを紹介します。ぜひ、防災グッズを揃える際の参考にしてください。
飲料水
飲用や調理用の水は、1人1日3リットルを目安に、最低3日分、できれば1週間分を備蓄しておくと安心です。在宅避難用であれば2リットルのペットボトルで十分ですが、一時避難用には重いため、500ミリリットルのペットボトルも用意しておくと便利です。持ち出し用リュックには2本程度入れておきましょう。
非常食
温めなくてもそのまま食べられる缶詰やレトルト食品を中心に、1人5食分程度を用意します。被災生活で不足しやすいビタミンがとれる野菜ジュースやフルーツの缶詰や、子どもにはおやつやお菓子、高齢者には食べやすいレトルト食品のおかゆなど、家族構成にあわせて選びましょう。
なるべく普段の食生活と変わらない内容を維持できるよう、缶詰などを多めに買い置きして定期的に消費していく「ローリングストック」という備蓄法で管理するのがおすすめです。
▼こちらもご参考ください。
ローリングストックの実例集|食品・日用品・燃料を無理なく備える方法を紹介
カセットコンロ
過去の災害では、お湯が沸かせなくて赤ちゃんのミルクを作るのが大変だったという声もあります。災害時でもお湯を沸かせるよう、カセットコンロも準備しておくと安心です。ガスや電気が止まっても調理ができる他、お湯で濡らしたタオルで体を拭いたり、消毒に使ったりと幅広い用途で活躍します。
モバイルバッテリーやポータブル電源
災害時は情報収集や連絡を行うためにスマートフォンが欠かせません。モバイルバッテリーに加え、容量の大きいポータブル電源を用意しておくと、より安心です。
ライトやランタン
在宅避難時の照明器具は、家族の人数分を用意しておくと安心です。手元や足元を照らす懐中電灯や小型ライトの他に、周囲を明るく照らせるランタンも備えておくと、夜間の作業や生活がスムーズになります。
救急用品や衛生用品
ばんそうこうや消毒薬などの救急用品、トイレットペーパーやティッシュペーパーなどの衛生用品は、1週間分のストックが必要です。場所を選ばずに用を足せる携帯トイレやポリ袋、ウェットティッシュなども準備しましょう。
その他に常備薬や風邪薬、鎮痛剤などの医薬品は、3日~1週間服用できる量を準備します。女性の場合は生理用品、子どもや高齢者のおむつ、ペットのトイレシートなども忘れずに備えておくことが大切です。
燃料
災害グッズとして意外と見落とされがちなのが燃料です。まず車の燃料は、車中避難をする際に冷暖房や充電設備を使うためにも十分に確保しておく必要があります。過去の災害では、ガソリンスタンドに人が殺到するケースも少なくありませんでした。
また灯油の備蓄も重要です。寒い時期にライフラインが停止すると、エアコンや床暖房が使えず、低体温症のリスクが高まります。そんな時、石油ストーブがあると便利です。普段から灯油を備蓄している寒冷地でも、万が一に備えて1缶多めに用意しておくことを心がけましょう。
本当に必要な防災グッズを見極めるポイント

防災グッズは、自分や家族の生活スタイルや年齢に合わせて選ぶことが大切です。必要なものと不要なものを見極めることで、無駄な出費を防ぎながら効率良く準備できます。
家族構成・生活スタイルで必要なものを考える
子どもや高齢者がいる家庭は保温グッズや医療・衛生用品を優先し、ペットがいる家庭は携帯用の食器やフードの備蓄、ケージやキャリーなどを準備します。アレルギーや食事制限がある家族がいる場合は非常食の選定にも注意が必要です。普段から家族が使い慣れているものを選ぶことで、災害時の混乱を減らせます。
防災グッズは3段階で考える
防災グッズは種類が多いので、次の3段階に分けて準備すると効率的です。
- 緊急避難用
すぐに持ち出せるリュックに貴重品、身分証、常備薬など最小限の必需品を入れる
- 災害発生から3日間用
避難所で必要な水や食料、衣類、携帯トイレ、懐中電灯などを揃える
- 在宅避難用(1週間程度)
水や食料の備蓄に加え、カセットコンロやランタン、日用品などを準備する
このように段階ごとに整理すると、「何をどこに置くか」「どの順番で持ち出すか」が明確になり、効率良く揃えられます。
地域の災害リスクを確認する
自分が住む地域で起こりやすい災害を把握することは、必要な防災グッズを見極める上で非常に重要です。
- 水害が多い地域
浸水に備えた防水袋の用意や、2階への避難経路を考慮する
- 土砂災害の可能性がある地域
自宅への浸水を想定して防災グッズを2階以上に置くなどの対策が有効です。
- 地震が多い地域
家具の転倒防止や非常食・飲料水の備蓄を優先する
このように、地域ごとの災害リスクに合わせた備えを選ぶことで、効率良く必要な防災グッズを揃えられます。
優先順位をつける
防災グッズは種類が多く、一度にすべて揃えるのは大変です。そのため優先順位の高いものから準備することが大切です。まずは命を守るための水や食料、情報収集、保温グッズなどの必需品を揃え、その次に衛生用品や調理器具、衣類などを検討します。
家族の人数や年齢、ライフスタイル、収納スペースを考慮しながら優先順位を決めると、無駄な買い物を防ぎながら効率的に備えを整えられます。また防災グッズを定期的に見直すことも忘れないようにしましょう。
いらなかった防災グッズを参考にして、必要な備えを進めよう

防災グッズは準備しても、実際に被災してみると案外「いらなかった」と感じるものがあります。災害時の使い勝手や生活スタイル、住んでいる地域に合った本当に必要な防災グッズを自らの目で見極めて準備することが大切です。そうすることで、効率良く備えを進めて安心を手に入れられるでしょう。
#ライフスタイル
#防災グッズ
合わせて読みたい
-

2025/12/25
灯油
【灯油の入れ方ガイド】ポンプの使い方やこぼしてしまった時の対処法...
#灯油 #灯油保管
-
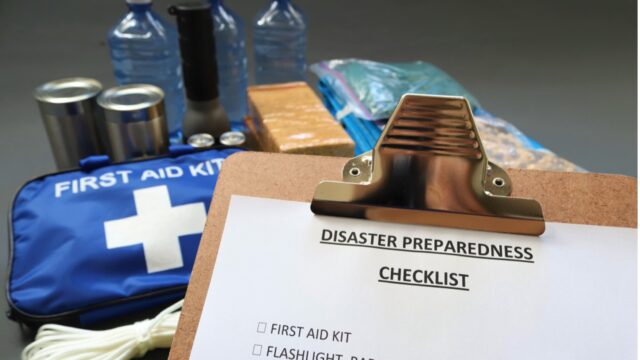
2025/11/27
ライフスタイル
防災備蓄品リスト完全ガイド|家庭と企業で備える必需品と管理のコツ
#日常生活 #防災グッズ #防災備蓄
-

2025/11/25
ライフスタイル
ポリ袋調理で災害時も温かい食卓を。備蓄食材を活用した非常食レシピ集
#日常生活 #防災
-

2025/11/13
ライフスタイル
ローリングストックで備える非常食|適した食品や実践のポイントを解説
#ライフスタイル #ローリングストック
-

2025/11/01
ライフスタイル
遊びが“備え”に変わるとき。アウトドアの達人に聞く“楽しく防災”の始...
#アウトドア #インタビュー #有識者
-

2025/09/18
ライフスタイル
ローリングストックの実例集|食品・日用品・燃料を無理なく備える方...
#ローリングストック #燃料備蓄 #防災 #防災備蓄



