
日常に“少しの備え”を。瀧本真奈美さんが実践する、無理なく続く防災習慣
「いざというときに慌てないために、日頃からの備えが何よりも大切です」と語るのは、愛媛県在住のライフスタイルアドバイザー・瀧本真奈美さんです。今回は瀧本さんに、忙しい毎日のなかでも無理なく続けられる”防災習慣”についてお話をうかがいました。
| 瀧本真奈美さんのプロフィール 正看護師として約20年勤務したのち、整理収納コンサルタントや防災士の資格を取得。現在は株式会社クラシングR代表取締役として、心地よく安全な暮らしを提案し続けている。SNSのフォロワーは約20万人。日々の投稿では、防災アイテムの選び方や収納術、日常の中で無理なくできる備えの工夫が多くの共感を集めている。 |
片づけの原点と、防災士への道

「子どものころは、家の中にあふれた物をまたいで歩くのが当たり前の暮らしだったんです」
と、少しいたずらな笑顔で語る瀧本さん。現在のSNSの投稿や著書で拝見する、スッキリ整頓された居心地のよさそうなインテリアからは、想像もつきません。
そんな瀧本さんの整理収納の原点は中学時代。友人の家に遊びに行ったとき、出した物がすっと元の場所に戻っていく様子を見て「まるで魔法みたい」と感じたといいます。そこでまずは自室の、お気に入りのリップを入れている引き出しから片付けを試してみました。
「片付けることで、引き出しを開けるときのワクワク感や使いやすさを実感して以来、ずっと整理収納に携わっています」
その後、看護師として現場に立つなかで、“命を守る暮らしかた”を意識するようになった瀧本さん。災害が起きても「備えさえあれば助かる命もあるのではないか」と痛感したそうです。
「大きな災害の後には、人が食べ物を奪い合うような悲しい場面もあります。でも、自分に余力があれば誰かに分け与えることができる。そんな『与え合える社会』にするためにも、一人ひとりが日頃から備えておくことが大切なんです」
防災意識が一気に高まったのは、2016年の熊本地震がきっかけ。とても身近に感じたことで「地震は日本のどこでも起こりうる」と実感し、収納の工夫と防災を掛け合わせた発信を始めるようになりました。
「発信を続けるなかで、言葉に責任を持つため防災士の資格を取りたいと思うようになったんです。2022年のコロナ禍で仕事が落ち着いたので、このタイミングで資格を取得しました」
“収納と点検”をセットに。防災を日常の一部に

「防災は特別なことではなく、習慣化させて忘れないこと、そして家族と共有することが大切です」
そう話す瀧本さんが行っているのは“月に一度の防災点検ルーティン”です。防災グッズの賞味期限や使用期限の確認はもちろん、何をどこに入れているのかを記憶し直すことも欠かせません。
見直すことで「これ足りないな」「ここにあった方が便利かも」と気づくきっかけにもなるため、新しい備品を追加するタイミングとしても活用しているそうです。また物を追加したり動かしたりしたら、家族と必ず共有します。
「『こういうものを買ったよ』『あなたのリュックはここにあるよ』など、定期的に会話をしたり、一緒に物を入れ直したりして防災を自分ごとにしてもらうように意識しています。実際に自分で触れておかないといざというときに動けないですし、そのときに伝えられる時間がないかもしれないからです」

瀧本さんは、防災グッズを1箇所に集中させることへのリスクも指摘します。その場所が潰れてしまうと取り出せなくなる可能性があるため、寝室や玄関、キッチンや車内など複数の場所に分散させることが重要だそうです。
「何も備えていないと、何か起きたときに不安感や恐怖が大きくなります。だからこそ、『これだけ備えてあるから大丈夫』と、自分に言い聞かせられるだけの準備をしておくことが心の安心につながるんです。小さなお子さんがいらっしゃる方は、お子さんにも理解しやすい言葉で説明することや身長に合わせた持ち物を備えるなどの工夫をしてあげるといいですね」
さらに瀧本さんは、日頃の備えを家の外にも向けてみてほしいと言います。無理なく始められる備え、それが“ガソリン満タン”です。
車社会だからこそ“ガソリン満タン”が安心につながる

深夜23時、突然スマホから鳴り響いた緊急地震速報。そのとき瀧本さんの脳裏によぎったのは、ガソリンのことでした。
「ガソリンが少なかったのが気になって、しばらくしてから給油に行きました。実際には大きな地震ではありませんでしたが、もし本当に大きな地震だったらパニックバイが起こっていたかもしれないですよね。事前に満タンにしておくべきだったと、強く思いました」
この経験から、瀧本さんはガソリン残量を常に気にかけ、無理のない「満タンルーティン」を生活に組み込んでいます。
「わざわざ入れに行くと、かえってガソリンを消費してしまいますよね。だからこそ、移動の合間に給油できるよう、スタンドの場所をチェックしておいたり、買い物帰りの給油を習慣にしたりしています」
こうした小さな工夫の積み重ねが、いざというときの安心につながるという瀧本さん。日頃からガソリンを満タンにしておくことで、緊急地震速報が流れても焦らなくなったといいます。
「みんなが日常的にガソリンを入れていれば、いざというときに給油の列に並ぶ必要もありません。災害が起こるだけでもパニックになるのに、パニックバイが起これば不安や恐怖はもっと大きくなりますよね」
防災は何か特別なことをするのではなく、いつもの生活の中で少し意識するだけでも十分始められることがある。そう瀧本さんは教えてくれました。
「『自分の地域ならどうする?』と想像することも大切です。『地震が起きたのは他の地域だから関係ない』ではなく、自分の地域に置き換えて考えてみてほしい。防災意識はそこから育つと思います」
防災意識をもっと身近に。SNS発信に込める思い

「物価高で家計が厳しいなか、防災のために新しいアイテムを揃えるのは正直ハードルが高いですよね。日常をこなすだけでも大変なので、いつ来るかわからない災害のための出費はどうしても後回しになってしまう。だからこそ、少しずつやるのが大切なんです」
実際に、SNSでの発信を通して「防災のハードルが下がった」と感じる声も少なくありません。ある投稿で、食器の収納場所を背の高い食器棚からシンク下へ移したことを紹介したところ、それを実践した読者から「地震が来ても、お皿が一枚も割れなかった」とのメッセージが寄せられたそうです。

「熊本地震の際には、実際に車中泊をされていた方からメッセージをいただいたことがありました。そのときにお子さんがとても怯えていたという声を聞いて、精神面でのケアについてももっと伝えていく必要を感じました。看護師時代に精神科にもいたので、少しでも心を和らげる発信ができたらと思っています」
防災を”こわいもの”としてではなく、”暮らしを見直すきっかけ”として伝えたい。自分の発信が誰かの参考になったり、背中を押したりできるかもしれない。瀧本さんは今後も発信を続けていきたいと話します。
「防災意識はまだまだ十分ではないと感じています。セミナーでお話しさせていただいても、『うちには関係ない』『このあたりは災害が少ないから』といった反応もあります。起こってからでは遅いし、今まで起こっていないから大丈夫ということもありません。もし『自分の家で起きたら?』『外で過ごすことになったら?』って、日頃から想像しておくことが本当に大事だと思います」
「できることから始めていい」無理なく備えよう

防災はできることからでいいし、完璧である必要もない。瀧本さんが大切にしているのは、そんな無理のない考え方です。
まずは“自分で備える”ことが防災のスタート。家族がいる場合は、「自分だけが知っていればいい」ではなく、全員で共有しておくことも大切です。家庭内で防災意識を高めるには、セミナーやイベントに一緒に参加するなどして情報を取りに行くことも一つだと瀧本さんはいいます。
「自分が備えられているからこそ、人を助けることができ、社会全体として助け合える。その輪が広がれば、どんな災害も少しずつ乗り越えていけると思います」
#日常生活
#災害対策
#防災
合わせて読みたい
-
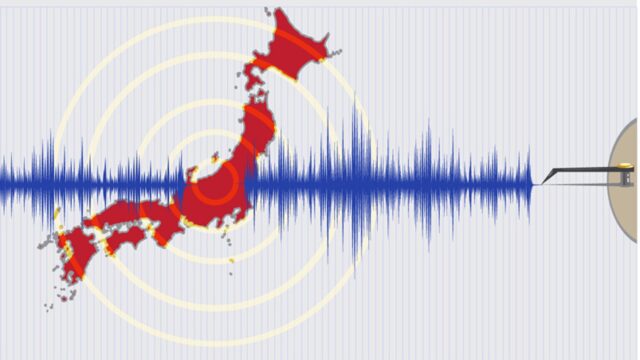
2025/12/16
南海トラフ
首都直下地震はいつでも起こりうる!発生確率や想定被害、今できる備...
#地震
-
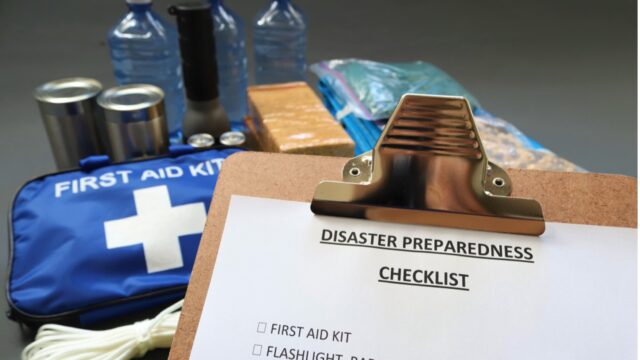
2025/11/27
ライフスタイル
防災備蓄品リスト完全ガイド|家庭と企業で備える必需品と管理のコツ
#日常生活 #防災グッズ #防災備蓄
-

2025/11/25
ライフスタイル
ポリ袋調理で災害時も温かい食卓を。備蓄食材を活用した非常食レシピ集
#日常生活 #防災
-

2025/11/13
ライフスタイル
ローリングストックで備える非常食|適した食品や実践のポイントを解説
#ライフスタイル #ローリングストック
-

2025/11/01
ライフスタイル
遊びが“備え”に変わるとき。アウトドアの達人に聞く“楽しく防災”の始...
#アウトドア #インタビュー #有識者
-

2025/10/16
ライフスタイル
防災グッズでいらなかったものとは?本当に必要なもの7選も紹介
#ライフスタイル #防災グッズ



